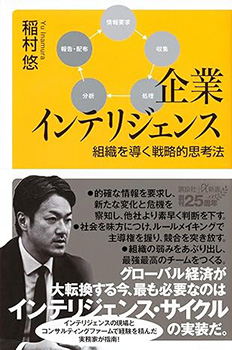地政学リスクの増大、サプライチェーンの脆弱化、そして激化する技術覇権争い。現代の企業経営は、かつてないほど複雑で予測不可能な環境に直面しています。従来の経験と勘に頼った意思決定はもはや通用せず、多くの企業が戦略的な方向性を見失いかけているのが実情です。このような時代において、組織が生き残り、そして勝ち抜くために不可欠な能力こそが「企業インテリジェンス」です。
本書は、その企業インテリジェンスを組織に実装するための、極めて実践的な手引書です。著者の稲村悠氏は、警視庁公安部で諜報活動の捜査に従事した経験を持つ国家インテリジェンスの実務家でありながら、その後大手コンサルティングファームで経済安全保障や地政学リスク対応の最前線に立ち、現在は経済安全保障対応からサイバーセキュリティまで幅広い支援を手掛けるコンサルティングファームを立ち上げ、代表を務める稀有な経歴を持ちます。国家レベルの情報分析手法と、民間企業の戦略課題を知り尽くした「実務家」だからこそ描ける、机上の空論ではない、現場で機能するインテリジェンスの設計図がここにあります。
本書が提示する核心は、インテリジェンスを単なる「守り」のリスク管理ツールとしてではなく、「攻め」の競争優位を確立するための戦略的武器として捉え直す視点です。的確な情報要求に基づき、組織全体で情報を価値ある「インテリジェンス」へと昇華させるプロセス、すなわち「インテリジェンス・サイクル」を回すことで、企業は未来を予測し、市場のルールを自ら形成し、競合を突き放すことが可能になると本書は説きます。これは、すべてのリーダーが学ぶべき、21世紀の新たな経営の教科書と言えるでしょう。
【目次】
- 第一章 日本企業のインテリジェンス・サイクルは機能しているか
- 第二章 新しいインテリジェンス・サイクルの形
- 第三章 インテリジェンス・サイクルの成功を握る鍵
- 第四章 インテリジェンス・サイクルに必要な人材と能力
- 第五章 「守り」のインテリジェンス・アプローチ――リスク・インテリジェンス・サイクル
- 第六章 「攻め」のインテリジェンス・アプローチ――インテリジェンス・アプローチ1
- 第七章 企業が主体となって社会を変える――インテリジェンス・アプローチ2
- 付録1 インテリジェンスにおける情報取扱適格性チェックリスト
- 付録2 意思決定者向けレーダーチャート インテリジェンス担当者向けレーダーチャート
本書から学べる3つの核心
-
「インテリジェンス・サイクル」という実践的フレームワーク
本書が提示する最も重要な概念が「インテリジェンス・サイクル」です。これは、単なる情報収集やデータ分析とは一線を画します。その起点は、経営トップが戦略的課題に基づき発する的確な「情報要求」にあります。この「正しい問い」を立てることで初めて、組織は膨大な情報の中から価値あるものを抽出し、分析・評価を経て、意思決定に資する「インテリジェンス」を生成できるのです。本書はこのサイクル(要求→収集→分析→報告→フィードバック)を組織に定着させるための具体的な手法を指南します。これは、多くの企業が陥る「データは豊富だが、知見が不足している」という状況を打破し、受動的な情報収集から能動的な戦略的探求へと組織を転換させるための、強力な処方箋です。
-
「攻め」と「守り」を両立させるインテリジェンスの二元戦略
本書は、インテリジェンスの役割を「守り」と「攻め」の二つの側面に分けて解説しており、これが極めて戦略的です。「守り」のインテリジェンスとは、経済安全保障、技術流出、サプライチェーン寸断といった事業継続を脅かすリスクを早期に察知し、対応策を講じるための活動です。一方で、本書が特に強調するのが「攻め」のインテリジェンスです。これは、新規事業の創出や新市場開拓はもちろん、ロビー活動や標準化戦略を通じて社会や業界の「ルールメイキング」で主導権を握り、自社に有利な事業環境を能動的に創り出すための活動を指します。この二元戦略を実践することで、企業はリスクに強い体質を構築すると同時に、持続的な競争優位性を築くことが可能になります。
-
インテリジェンスを支える「組織文化」と「人材」の育成法
優れたフレームワークも、それを動かす組織と人材がなければ絵に描いた餅に過ぎません。本書の価値は、その「人」と「文化」の側面にも深く踏み込んでいる点にあります。第四章「インテリジェンス・サイクルに必要な人材と能力」では、どのようなスキルセットを持つ人材を育成・確保すべきかが具体的に論じられます。さらに、付録として収録されている「情報取扱適格性チェックリスト」や「意思決定者向けレーダーチャート」といったツールは、組織全体のインテリジェンス・リテラシーを向上させ、共通言語を醸成するための実践的な武器となります。専門部署を設置するだけでなく、経営層から現場まで、すべての階層がインテリジェンスの重要性を理解し、サイクルの一翼を担う文化をいかにして築くか。そのための具体的な道筋が示されています。
経営者・経営企画の皆様へ:本書がもたらす3つの経営変革
-
不確実性を乗りこなす「戦略的先見性」の獲得
経営の舵取りが最も困難な現代において、本書は「新たな変化と危機を察知し、他社より素早く判断を下す」ための体系的な方法論を提供します。インテリジェンス・サイクルを経営の中枢に組み込むことで、経営陣は単なる過去データの分析から脱却し、未来の兆候を捉えることができます。これにより、競合他社が後追いで対応するような地政学リスクや市場の構造変化を先読みし、先手を打つことが可能になります。これは、受動的なリスク管理から、未来を能動的に形作る戦略的意思決定への質的転換を意味します。
-
危機に強い「システミックな組織的耐性」の構築
インテリジェンス機能は、一部の専門家だけのものではありません。本書が示すアプローチは、財務管理や法務コンプライアンスと同様に、企業統治の根幹をなすべき機能です。組織の弱点を平時からあぶり出し、技術流出や経済安保上のリスクに体系的に備えることで、有事の際に致命傷となりかねない脆弱性を事前に解消し、組織全体のレジリエンス(回復力・弾力性)を飛躍的に高めます。これは、単発の危機対応ではなく、持続可能な事業基盤を構築するための本質的な投資です。
-
競合を無力化する「非対称な競争優位」の確立
製品やサービスの優位性はいずれ模倣されますが、優れたインテリジェンス能力は容易に模倣できない、真の戦略的資産です。本書が説く「攻め」のインテリジェンス、特に「ルールメイキングで主導権を握り、競合を突き放す」という思想は、競争の次元そのものを変えるものです。市場というゲーム盤の上で戦うのではなく、ゲームのルール自体を自社に有利なように設計する。この「企業版の国家戦略」とも言えるアプローチを実践することで、他社が追随できない非対称な優位性を確立し、持続的な成長と収益性を確保することが可能になります。
事業部長・現場リーダーの皆様へ:本書がもたらす3つの現場変革
-
部門の壁を越える「戦略的共通言語」の導入
「あの部署が何を考えているかわからない」といった組織のサイロ化は、多くの企業の課題です。インテリジェンス・サイクルは、この問題を解決する強力なツールとなります。経営トップからの「情報要求」という明確な目標が共有されることで、各部門は自らの業務が全社戦略のどの部分に貢献するのかを明確に認識できます。本書が示すサイクルは、「組織全体を束ね、的確な方向性を示すコンパス」として機能し、部門間の連携を促進し、真に戦略的な協業体制を現場レベルで実現します。
-
チームを成長させる「高付加価値な分析能力」の開発
チームのメンバーを、単なる情報収集者から、意思決定に貢献するインテリジェンス生産者へと成長させたいリーダーにとって、本書は格好の教科書です。第四章で詳述される「必要な人材と能力」や、付録の「インテリジェンス担当者向けレーダーチャート」を活用すれば、チームメンバーの現状スキルを評価し、育成計画を具体的に立てることが可能になります。これにより、チーム全体の分析能力と戦略的思考力を体系的に向上させ、より付加価値の高いアウトプットを生み出す組織へと変貌させることができます。
-
企画を通すための「論理的で説得力のある根拠」の構築
新規プロジェクトや予算獲得の際、その必要性を客観的かつ説得力をもって説明することは、現場リーダーにとって重要なスキルです。インテリジェンス・サイクルは、そのための最強の武器となります。自らの提案を、経営陣が発した戦略的な「情報要求」に対する、厳密な情報分析に基づいた「回答」として位置づけることで、その正当性と重要性は飛躍的に高まります。これにより、単なる思いつきや希望的観測ではない、データと論理に裏打ちされた強力なビジネスケースを構築し、経営層の承認を得やすくなります。