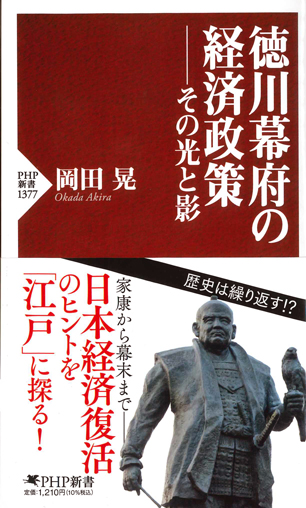「士農工商の身分制度」「閉鎖的な鎖国体制」「重い年貢」――。私たちが学校で学んだ徳川幕府のイメージは、果たして真実なのでしょうか。260年以上にわたり、奇跡的な平和と安定を維持した江戸時代。その基盤には、現代の常識をも超える、したたかで合理的な経済システムが存在していました。しかし、その政策は本当に民を豊かにしたのか、それとも衰退へと向かう宿命を背負っていたのでしょうか。
本書が描き出すのは、固定観念を覆す、ダイナミックな江戸の経済社会です。著者は、経済記者として長年マーケットの最前線を見つめてきた岡田晃氏。その鋭い視点から、徳川幕府が展開した経済政策の実像を「光」と「影」の両面から丹念に解き明かします。単なる過去の歴史としてではなく、現代日本の経済システムや政策のルーツを探るための、新たな視座を提供します。
本書の力強いメッセージは、「世界最高の経済システムは、なぜ崩壊したのか」という根源的な問いに集約されます。金銀の国際収支、米価の安定、度重なる財政危機との闘い。これらの政策決定の裏側を知ることは、現代を生きる私たちが経済の本質を理解するための、最高のケーススタディです。本書を読めば、歴史に埋もれた経済のダイナミズムを感じ、現代社会を読み解くための「歴史の羅針盤」を手に入れることができるでしょう。
【目次】
- 第一章 家康の経済戦略〝エドノミクス〟
- 第二章 幕府を揺るがした政治危機と大災害
- 第三章 〝元禄バブル〟の実相
- 第四章 正徳の政――〝バブル〟崩壊でデフレ突入
- 第五章 吉宗の「享保の改革」――元祖・リフレ政策
- 第六章 田沼時代の真実――成長戦略と構造改革の試み
- 第七章 「寛政の改革」――超緊縮で危機の乗り切りを図るが……
- 第八章 「化政バブル」――〝最後の好景気〟
- 第九章 「天保の改革」――〝最後の改革〟だったが……
- 第十章 幕府崩壊と近代化の足音
本書から学べる3つの核心
-
「鎖国」のイメージを覆す、巧みな国際経済戦略
本書は、幕府が初期に行った金銀の輸出が、国内に莫大な富をもたらした「光」の側面を明らかにします。しかし、その後の金銀枯渇という「影」に対し、新井白石らが貿易量を制限し、国内の資源を守ろうとした防衛的な経済政策へと転換する過程を詳述。「閉鎖的」と一括りにされがちな鎖国政策が、実は国際収支を意識した、極めて戦略的な判断であったことを理解できます。
-
貨幣改鋳とデフレ・インフレを巡る幕府の苦闘
景気浮揚のために行われた元禄の貨幣改鋳(インフレ政策)と、その後の財政再建のために断行された緊縮財政(デフレ政策)。本書は、荻原重秀、新井白石、徳川吉宗といったキーパーソンたちの政策を追いながら、現代にも通じる金融政策の功罪を、江戸時代という壮大な実験場から学ぶことができます。経済の安定と成長のバランスをどう取るかという、普遍的な課題が浮かび上がります。
-
「悪役」ではない、田沼意次の先進的な経済手腕
賄賂政治の象徴として語られがちな田沼意次。しかし本書は、彼が重商主義政策を推し進め、商業の活性化や新田開発、貿易の拡大を図った先進的な経済閣僚であった側面を再評価します。保守的な勢力との対立の中で、既得権益を打破し、経済成長を目指した改革者の苦悩とビジョンを読み解くことで、田沼政治の新たな実像に迫ります。
歴史の見方が変わる:本書がもたらす3つの視点
-
江戸時代への固定観念が覆り、見方が立体的になる
本書を読めば、「停滞した封建社会」という江戸時代のモノクロなイメージは一変します。幕府が、現代と変わらぬ財政赤字やデフレ、国際競争といった課題に、いかに知恵を絞って立ち向かったかを知ることができます。歴史上の人物たちが、生身の人間として経済問題に格闘する姿が見え、歴史がより身近でダイナミックなものに感じられるようになります。
-
現代日本の経済問題を考える「歴史の物差し」を得る
金融緩和、財政赤字、産業の保護と育成――。本書で描かれる江戸時代の経済政策は、驚くほど現代の私たちが直面する問題と似ています。歴史という鏡を通して現代を眺めることで、目先のニュースに一喜一憂するのではなく、より長期的で大局的な視点から、今の日本の経済政策を評価する力が養われます。
-
経済ニュースの「なぜ?」が、歴史的文脈で理解できる
なぜ日本は特定の産業構造を持つに至ったのか。なぜ為替や金利の変動に一喜一憂するのか。その原型は、江戸時代の経済システムに多く見出すことができます。歴史を知ることは、現代経済の根底に流れる「思想」や「体質」を理解することに繋がります。日々の経済ニュースの背景にある、より深い文脈を読み解く面白さを発見できるでしょう。
現代の経営者が江戸に学ぶ、不変の『組織経営』3つの原則
-
長期安定と硬直化に学ぶ、持続的成長の経営戦略
260年という世界史上稀に見る長期安定を達成した徳川幕府。その初期の成功モデル(金銀輸出)が、やがて資源枯渇という危機を招きます。経営者は、創業期の成功体験が、環境変化の中でいかにして足枷となり得るかを学べます。短期的なキャッシュフローと、長期的な事業基盤(国力)の維持という、二律背反する課題にどう向き合うか。企業の持続的成長を考える上で、歴史からの普遍的な教訓を得られるでしょう。
-
財政危機におけるリーダーの決断と経済感覚
緊縮財政で立て直した新井白石、インフレ政策で景気浮揚を図った荻原重秀、米価の安定に腐心した徳川吉宗。本書は、幕府という巨大組織の財政危機に際し、リーダーが下した経済政策の「決断」とその結果を克明に描きます。これは、不況下のコストカットか、未来への投資かという、経営判断そのものです。リーダーの経済センスと哲学が、組織の運命をいかに左右するかを追体験できます。
-
田沼意次の改革に学ぶ、イノベーションと抵抗勢力
旧来の価値観(農本主義)が支配する中で、商業を重視し、既得権益と戦いながら改革を推し進めた田沼意次。彼の姿は、旧弊がはびこる組織で新規事業や業務改革を断行しようとする現代の経営者・管理職の姿と重なります。改革には痛みが伴い、必ず抵抗勢力が生まれるという現実を直視し、それでも未来のために変革を断行する覚悟とは何か。そのリアルな葛藤と戦略を学べます。